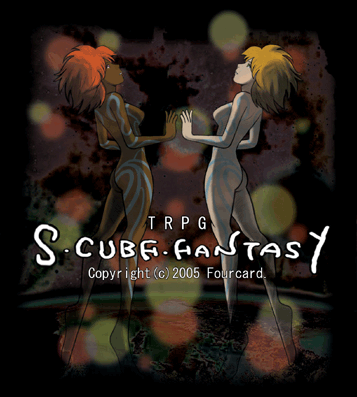
(イラスト:BLACK)
はじめ、世界にはリト神と巨大なマナのかたまりだけが存在した。
太陽と光を司るリト神がどうやって生まれたのかは、誰も知らない。
リト神は、マナを削り取って球体を作り「大地」と名付けた。
そして大地のいたるところに、マナから生み出した四元素「火・水・風・土」を宿らせた。
リト神は、さらにマナを削ると、さまざまな生命をつくりだした。
植物、魚、鳥、獣、そしてエルフ。
彼らは大地のちょうど半分、リト神の光が照らしだす光の半球で平和に暮らした。
あるとき、ダルクという名の女エルフが、マナの力に興味を持った。
彼女は、忠実に仕えるふりをしてリト神に近づくと、マナのかけらを少しずつ掠め取った。
そうして集めたマナのかけらは、闇の半球に蓄えていった。
闇の半球は、リト神の光に照らされることのない暗黒の地。
誰にも気づかれる心配がなかった。
十分なマナを手に入れたダルクは、見よう見まねで生命を作ってみた。
ところが、何度やってもうまくいかず、恐ろしげな異形の怪物たちばかりが生まれた。
怪物どもをもてあましたダルクは、光の半球に逃げ戻ろうとして愕然とした。
闇の半球に長くいたあまり、彼女の肌の色は闇の色へと染まっていたのだ。
光の半球には戻れないと悟った彼女は、エルフ族を闇の半球へと引き込みはじめた。
一部のエルフはダルクの誘いに乗り、闇の半球へ渡った。
こうして、ダルクを頭とするダークエルフの一族が生まれた。
ダークエルフたちは、リト神の目の届かぬのを良いことに欲望のままに生きた。
これに気づいたリト神は怒り狂い、大地を一定の速度で回転させ続けることにした。
一日と置かず、大地の隅々までをみずからの光に照らそうというのだ。
こうして大地に昼と夜ができた。
ダルクたち闇の勢力は、リト神の眼から逃れ切ることができなくなった。
堕落の快楽を知ったダルクは、光を避けて逃げ回ることをよしとせず、反撃に転じた。
リト神が闇の生き物を駆逐しているときを狙って、大量のマナを奪い取ったのである。
そして、その強大なマナをもとにみずからの力を強めた。
そればかりか、新たに異形の怪物たちを大量に生み出しては、それらを支配した。
こうしてダルクは、強大な力を持った暗黒神となった。
リト神もダルク神も、マナを奪われまいとして、その傍らを離れられなくなった。
戦いは、大地に生きる者たちに委ねられた。
リト神は、闇の勢力に対抗すべく、あらたな種族を生み出した。
闇の中でも眼が利き、頑健な肉体を誇るドワーフ。
小さな身体で素早く駆け、敵の目を欺く機知に長けたミゼット。
そして、凡庸ながらも進取の気性に富み、よく学ぼうとする人間。
光の勢力は、協力して戦った。
エルフは弓と矢を手に、裏切り者を追い詰めた。
ドワーフは頑丈な肉体と厚き信仰を鎧として、その斧を振るった。
ミゼットは巧みに罠を操り、闇が闇の勢力以外にも与することを思い知らせた。
人間の武器は、その柔軟な精神と順応性であった。
彼らは、他の種族たちの長所に学んでは、目覚しい活躍を見せた。
しかし、ダルク神の勢力には、おぞましい怪物どもが名を連ねていた。
ダークエルフ、悪魔、巨人、邪竜、妖魔、魔獣…。
ダルク神が、マナから生み出した邪悪な生き物たち。
彼らは、夜の闇に乗じて光の勢力を蹂躙していった。
リト神は、光の勢力の中から特に信仰厚き者を選び、彼らを神格化することで対抗した。
一騎当千と恐れられた勇敢なる戦士、エグベル。
清く美しき慈愛の娘、リュー・リュー。
老いてなお学びを止めぬ大賢者、ユーセス。
普遍を見抜き不変を誇りしは、エルフのマロウ。
強き肉体に強き心を宿せしドワーフ、モシュロコ。
誰からも愛された小さき奇才、ミゼットのキリ。
残されたマナのすべてを注がれた彼らは、光の従属神と化して戦局を一変させた。
追い詰められたダルク神は、リト神のやり方を真似ようとした。
しかし闇の民には、光の民ほどの信仰心を持つ者がいなかった。
ダルク神がマナを使って神格化した闇の神々は、光の神々よりも劣っていた。
しかも闇の神々は自分勝手で、互いに協力し合うということがなかった。
ようやく闇の神々が手を取り合ったときには、すでに勝敗はつきかけていた。
やむなく、ダルク神はわずかに残ったマナを使って邪悪な怪物を生み続けて抗った。
しかし、それも単なる悪あがきでしかなかった。
永劫とも思える戦いが続いたが、光の勢力の勝利は時間の問題であった。
ついに、ダルク神の手元のマナが底をついた。
リト神と光の神々は、闇の神々をひとところに追い込み、これを滅ぼさんとした。
そのとき、破壊の神ウィルドナが、隠し持っていたマナのすべてを暴走させた。
暴走したマナは集まっていた神々をすべて呑み込み、その肉体を一瞬にして滅ぼした。
このとき大地へと霧散したマナは、生き物たちの内側へも深く浸透していったという。
すべてが終ったとき、肉体を失った神々にはもはや以前ほどの力が残っていなかった。
これ以上争ったところで決着がつかないことを悟った神々は、
大地の統治を大地の生き物たちに任せ、みずからは限定的にしか干渉しないことで同意した。
こうして、大地は神々の手を離れ、私たち大地に生きる者たちにゆだねられた。
邪悪なる闇の民は、私たちと同様にこの大地に生き残っている。
しかし、我ら光の民は、それに対抗する術を持っていないわけではない。
光の神々への信仰と知恵と協同――それこそが私たちの何よりの力となるだろう。